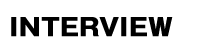連載インタビュー第2回「結成当時の音楽シーンとオリジナリティ」
第2回:結成当時の音楽シーンとオリジナリティ
(取材・文/西廣智一)

──CURIOを結成した当時はどういうことを考えて曲作りをしていたんですか?
AJ なんて言ってたっけなあ……結果全然違うことになったけど、あんまり汗だくにならないようにはやりたいなとは思ってたかな。全然そうなんなかったけど。
NOB めちゃくちゃ汗だくだよ、毎回(笑)。
BRITAIN そのへんAJはちゃんと考えながらやってたと思いますよ。ああしよう、こうしようってところはすごく発信してたし。
NOB やっぱりそういう指針があったのは大きかったですね。あの当時に流行っていた音楽というよりは、自分たちが子供の頃から聴いてきたルーツ的なものであったり、そういうところをまず発信していたし。と同時に、僕はみんなから新しい音楽もたくさん教えてもらってた。そこから曲ができていって、バンドのキャラクターというものがだんだん作られていったような。だからこういうバンドにしたいというよりも、まず曲ありきだったんです。
AJ そうだね。「ひまわり」と「新世界」の2曲が最初にトントンとできて、あの2曲がバンドの最初のカラーを決定した感じだと思うんです。で、そこから……30分くらいのライブをやるのに5、6曲欲しいからってことで、1stアルバム『HYBRID』に入ってるような曲が次々とできていって。「ライブでこういう曲が足りないから作ろう」みたいな感じで、1曲1曲増やしていったんですね。でも核になってるのはやっぱり「ひまわり」や「新世界」。「新世界」の後半の、アウトロって言っていいぐらいの第2部の部分が結構重要で、あれができたことがバンドの可能性を広げた気がします。
──90年代初頭のUKロック的というか、バンドのルーツを感じさせるアレンジですよね。
AJ そうですね、マンチェスターサウンドの名残というか。あのへんの流れを汲んだスタイルで大阪で活動してたのが、1つの核になってますし。当時は東京だとVenus Peter、大阪だとSecret Goldfishみたいなバンドがいましたけど、そういう先輩たちがやってきたUKサウンドの流れにある音楽を、もう少し明るくやりたかったんですね。やってる人間の性格ありきで音楽が決まってきたというか。最初はTHE STONE ROSESのコピーとかやったもんね。
BRITAIN そうだね。
AJ でも、ローゼズみたいにはならなかった(笑)。だけどローゼズの「One Love」は、「新世界」のアレンジの下敷きになってると思うんですけどね。
──確かに1stアルバムを聴くとあの当時のUKロックの香りやテイストが感じられます。そこから作品を重ねるごとに、どんどんCURIOならではのオリジナリティが構築されていったと。
AJ ですね。あと、CURIOはエピック(Epic/Sony Records)からデビューしたんですけど……契約したからというわけではなく……あのレーベルのアーティストが好きだったんですよね。CHARAさんやJUDY AND MARY、PUFFYはもちろんそうですし、さらにその先輩方がやってる音楽をよく聴いていて。ああいう演奏力がしっかりあって完成されたポップミュージックを生み出す才能を持つ人たちがすぐ近くにいたから、ライブを観させていただいて参考になった部分もたくさんあった。時代背景が結構大きいんですよね。1995年ぐらいだと小沢健二さんが大ヒットしてる時期なんでよく聴いてたし。
──CURIOがデビューした1997年頃って、日本のロックが変革期を迎えたタイミングだったんじゃないかと記憶してますが。
AJ そうですね。特に東京に来てビックリしましたもん。何にビックリしたかって、やっぱり「AIR JAM」ですよ。大阪にはなかったですから、ああいうスタイルのライブは。そういう意味でもHi-STANDARDには一番ビックリしました。世代的には先輩ではありますけど、同時代に音楽をする者として「うわあ、すごい!」って単純に思いましたね。
「第3回:再結成後のCURIOが目指すもの」に続く。